春にDVDで鑑賞したホラー映画「ヘレディタリー」がとても好きな作品だったのだが、「ヘレディタリー」は1980年にアカデミー賞作品賞を受賞した「普通の人々」に影響を受けたとのこと…。
未見だったので、これを機会にと鑑賞してみたのだが、かなりの傑作だった。
ブログ初めて早々、鬱な家族の話ばかり書いている気もするが、語りたくて仕方なくなるような作品だったので、ネタバレ全開にしつつ、さっそく感想を書きなぐりたい。
長男を亡くした一家の不協和音
ジャレット一家はシカゴに住む、ごく普通の家族だった。
心優しい弁護士の父・カルヴィン、社交的な母・ベス、水泳部のエースの兄・バック、真面目な弟・コンラッド。
しかし、ある日、兄弟が湖に出かけた際、事故にあって、兄(長男)が溺死してしまう。
助かった弟のコンラッドもその後、自殺未遂をおこし、精神科に入院していたが、4か月後に退院。
全てがもとの生活へと戻りはじめているかにみえたが、コンラッドの心の中は重たく沈んだままだ。
息子を心配した父・カルヴィンは、コンラッドを精神分析医へと通わせるが、次第に、平凡なこの一家の本当の姿が明らかになっていく…。
事故で家族を亡くした者の心の痛みはもちろんのこと、兄の死を目撃したコンラッドのトラウマはいかほどか、常人には想像しがたい。
しかし、家族の死という事故は「この一家にもともとあった根深い問題」を露呈するきっかけになったにすぎなかった。
一体、この一家抱えている”問題”とは何なのか?
”ママは僕を嫌っている”
映画を観る前には、「なんか地味」としか思っていなかったポスタービジュアル…。
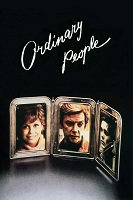
これがいかによく練られたものか、映画を観たあとだとよく分かる。
普通子供が真ん中に来そうなのに、”真ん中にいるのはお父さん”だ。
母親ベスの目線は家族の誰をもみていない。父親カルヴィンは息子へとどこか心配そうな目線を投げかけている。
そして息子・コンラッドはまるで故人かのように、色がない。
このコンラッドは一体なにに苦しんでいるのか。それは「母から愛されないこと」だった。
母親・ベスは、自覚なく、次男のコンラッドにかなり辛くあたっていた。
それは、おそらく兄の死の前からで、ベスは長男だけを”ひいき”してしまう母親だったのだ。
「彼女と通じない。」
・コンラッドが普通に、ベスに話しかけても、彼女がその意図を汲みとって、まともな返事を返してくれることは1度もない。
・1度もコンラッドを褒めたことがない。
子供に基本無関心なのだが、その反面、支配的な一面もある。
家族が神経科に通うことも快く思わない…部活を休まないように…などと、プレッシャーをかけてくる。
また兄の死を目の前にし、もっとも深い傷を心に負っただろうコンラッドのことを、微塵も心配しない。
多分、この家族、長男が生きていたときは、長男がみんなの橋わたし的存在・ムードメーカーに自然となれていて、そのおかげで何とか家族が保たれていたのだと思う。
単に”事故で家族を失って辛い”だけの一家の話ではない。
皆が実は依存していた、大きな支柱が欠けたことで、家庭が崩壊しようとしている家族の物語だ。
長男の代わりに真ん中に入ることになった父親・カルヴィンは、板挟み状態になり、心苦しい思いをしている。
皆でご飯を食べるとき…家族写真を撮るとき…日常の1コマ1コマが、ものすごく重苦しいものになっている。

自分は、母親ベスに嫌悪を感じた
この映画、ベスをどう評価するかは、意見が分かれそうだ。
「家庭の中の不穏をすべて母親の責任にするのはフェアではない」「相性の悪い親子というのは、親の方も不運なことだ」…自分もこのように感じる。
自分は「ヘレディタリー」のアニーには同情してしまったし、「クレイマー、クレイマー」の母(メリル・ストリープ)の気持ちもわかる…と思いながら観た人間だ。
しかし、この「普通の人々」の母親には、自分はかなりの嫌悪感を抱いた。
嫌だと思ってしまったところは、「外面がすべてにおいて優先されるところ」だと思う。
如実にそれがあらわれているシーンがいくつかある。
水泳部を辞めたことに怒った本当の理由
コンラッドが水泳の部活を両親に黙って辞めてしまっていた…それを両親が知って驚き、母親が責める…という場面がある。
「友達の前で恥をかかせたことがある?」
「可哀そうなのは私よ。息子のウソを信用して。」
父親・カルヴィンが、「水泳をやめてお前は本当によかったのか。報告してほしかった。」と息子に向き合うのに対し、ベスの方は、もう、「人からきかされて、母親の自分が息子について知らなかったのを、他人からどう思われたか。」という”自分のこと”に終始している。
コンラッドは賢いからこう返している。
「頭に来る理由はわかってる。人が先に知ってたからだ。」
”自分がどう思われるか”がベスにとって家族よりも1番大事なことなのだと思う。
家族がセラピーを受けていることをひた隠す
父親・カルヴィンがパーティーにて、息子コンラッドがセラピーを受けていることを他のお客に告白する場面がある。
しかしベスとあとから車で2人きりになると、カルヴィンは思い切りなじられる。
「なぜコンラッドのことを言ったの。」
「プライバシーの侵害よ!」「秘め事なのに。」
むやみやたらに家族のことを話さない方がいい、というのも分かる。そういう状況も多々ある。
しかし、この一家が「長男を亡くしたこと」も「次男が自殺未遂したこと」もみんなが知っている。招待客の中にはコンラッドを心配している人もいたと思う。
そんな中でも、ベスが懸念しているのは「家族の中に神経科なんぞに掛かっている人間がいると思われたくない。」というその1点だ。
カルヴィンに、「自分たち親もセラピーに参加してみては?」と提案されても、「私はまともな人間だからそういうのはいらない。」と突き返す。
自分たち家族の苦しみを認められず、「自分だけはまともで正しい」と言い張るところに、独善的な感じを抱いて嫌だなと思った。
辛いお葬式でも、服装を気にする
父親・カルビンが、突然思い立ったように、ベスを詰問するこの台詞も印象深い。
バックの葬式のときだ…。身支度していた私は、青いシャツを着た。そしたら、お前が白を着ろと。それがずっと心の隅に残っていた。そして、突然その理由が分かった。シャツの色がそんなに大事か。息子の葬儀で度を失っていた…なのにお前は服装を…。
こういう「外面がすべてにおいて優先される」というタイプの人が家庭の真ん中にいると、家族全員キツイと思う。
自分だけの行動を抑制している分にはいいが、人にもそれを強要してくると息苦しいことこの上ない。
特に、子供にとっては、自分の気持ちを素直に外に出せないというのは、シンドイ。その上、「自分で物事を考える力」を失くしてしまう。
「外面を異常に気にする」「支配的な」「兄だけをひいきし、自分への愛を示さない」母親の存在が、憂鬱の根源にあると、セラピーを通して次第にコンラッドは気付きはじめる。
感情が表現できなくなってしまったコンラッド
コンラッドが受けるセラピーは、俗にいう「アダルトチルドレン」の人たちの問題解決と同じプロセスだろうと思う。
セラピストを訪ねた当初、コンラッドは、「生ける屍」と先生から呼ばれてしまう。感情がないようだ…と。
腹がたっていても、怒れない。悲しくても、泣けない。
セラピストにのぞみを訊かれても、何が欲しいのかわからない。
優等生で、真面目で、なんの問題もない子供として育ってきた…と父に評されたコンラッド。
家庭の中で母親に気を遣い、「母の求める自分」をどこかで追いかけ、好かれようと必死だったのではないかと思う。
セラピーを通して、彼が少しずつ、感情を外に出せるようになり、怒鳴ったり、泣いたりができるようになってくる。
怒ることも、泣くことも、ある場面場面では、とても大事なことなのだ。
兄の死でも涙を流せななかった彼が、兄を愛していた…と号泣する場面には胸が締め付けられる。
途中、コンラッドの友人が自殺してしまい、最近たったの1回だけしか会わなかった彼が「なぜ気付いてやれなかった」と自分を責める場面もある。
また兄の事故死についても「もっと自分がこうすればよかった」という思いをひたすら持ち続けている。
「何かが起こると誰かが責任をとらなきゃ。」
「自分のせいで」と、ひたすら過去や他人に執着するのも、親の愛情を感じられなかった人の特徴ではないかと思う。
分析医が「よく考えてみろ。君だけの責任ではないだろ。」と諭していく場面もよかった。

最初、煙草プカプカ吸いながら結構ぞんざいな感じで、「この先生大丈夫かなあ~」と思ってゴメンナサイ。めっちゃいい先生で、コンラッド、ラッキーだった…!
”人間関係は自分で選べる”ものだと知る
またセラピーを通じて、コンラッドが学んだ大きなことは、「人間関係は自分で選べる」ということだ。
・大嫌いなコーチがいる水泳部を辞めた。嫌いな人間に好かれようとしなくていいのだ。
・自分が本当は好きな、性根のいい親友と離れることにした。いいヤツだと分かっているけれど、自分の苦悩を決して分かち合うことができない人だから。そんな彼の傍にいるのは自分にとって辛いことだから。
・自分の特技(よいところ)をありのまま認めてくれた、心優しいクラスメイトにアタックしてみることにした。彼女といると、素直に幸福を感じられるから。
「自分が楽」だと思えることを選択することができる。
(社会に出ると色々制約はあると思うが)人間関係は、本来、自分が主体的に選ぶことのできるものだ…これを知ったコンラッドはとても楽になったようにみえる。
家族という人間関係が上手くいかないのなら、そのほかの場所で、自分が幸せだと思える人間関係を自分でつくっていくしかない。
それは大変なことだが、その道があると知れたコンラッドには希望を感じる。
「ママの限界を知れ。」
残念ながら、「家族」とは自分が選択できない人間関係だと思う。
母親に愛されていないと絶望するコンラッドに精神科医がこう告げる。
「ママの限界を知れ。」
「愛が足りないのだ。彼女の愛には限界がある。」
「限界がある」という言葉、とてもいい。親に対してだけでなく、何に対してもいえることだと思う。
努力を放棄するわけではないが、努力してもどうにもならないことがあると知る。
自分が他者から理解されないのと同様に、自分もまた他者を知ることには限界がある。
コンラッドが映画終盤、母親をギュっと抱きしめるシーンがある。
鈍感な、あの母親でさえ、ただならぬものを感じて、目を丸くする。
あのシーンは、コンラッドが「大人」になった瞬間だった。
彼は自分を許し、自分に愛を示さない母親のことも「これが自分の母親だ。」と認めることができたのだ。
お互い決して好き合うことがないが、それが自分の家族であると認めることは、なかなか辛いことなのではないかと思う。このシーンは涙なしにみられない。
父親カルヴィンも、息子・コンラッドの変化を確かに感じとっていた。

カルヴィンはよい父親・よい夫だろうか?
こういう家族の物語の場合、「母親だけが悪いことはない。」「父親も何らかの責任はある。」…と評価されそうだ。
しかし、自分は個人的に、「普通の人々」の父・カルヴィンにはかなり好印象だ。
無干渉になるわけではなく、過干渉になるわけでもない。
本人の意思を尊重したいと思いつつ、時々気にかけていることを伝える。
この距離の取り方は間違っていないのでは、と思った。
しかしそんなカルヴィンでさえ、「家族の問題」を大きく誤って認識していたことが物語の途中で分かる。
カルヴィンは自らもセラピーを受けに行くが、「次男が母親と合わないのが問題」「ずっとコンラッドだけが異端…」というように口に出す。
「あーあ、分かってないんだ~。」ってなんか悲しくなっちゃったねえ。
しかし、セラピストに、「あなた自身は妻の愛を感じているか。」と問われ、言葉が少し詰まってしまう。
自身もどれだけベスに気を遣った異常な生活をしていたか、ようやく気付き、妻に本心を告げるシーンは切ない。
「言ってくれ、本心から私を愛しているか。」
「バックだけを愛していた。」
「バックではなく自分を愛していたのか。」
「君の正体がわからない。」
親子の物語かと思われた「普通の人々」は、最後、「夫婦の物語」も紡ぎだす。
「問題だったのは、親子関係だけではなかった。」「自分たち夫婦にも問題があった。」とこのお父さんが気付けたのは、自身が危機感を覚えて、素直に第3者の助けを得ようとしたからだ。
その点においても、(ベスと違って)このお父さんは悪くないなあと思う。
ラストはハッピーエンド!?だと自分は思った
映画のラスト、母親ベスは、なんのためらいもなく家を出て行ってしまう。
「向き合うために努力する」とか「自分を変えてみよう」とか、そういう行動をとらない”開き直り”は、ある意味、あっぱれである。
カルヴィンから責められ、居場所がなくなった、と感じた彼女は、なにもいわず、家を去っていく。
一家離散のアンハッピーエンドともとれるが、自分は「これが1番なのでは」と思った。
先ほど、「ベスを嫌悪する」と書いたが、自分の限界を知っている”自分に正直”なベスが「離れる」「逃げる」という選択肢をとったのは、とても賢いのでは、と思った。
きっと留まったほうが、全員、お互いに辛いはずだ。ベスはとても合理的な人間なのかもしれない。
家族には色々なかたちがあってもいいと、自分も思う。
ラストのコンラッドと父の場面にも号泣だ。
「愛している」という台詞がこんなに胸に響く作品は他にないかもしれない…と思うくらいすごかった。
「普通の人々」の類似作品いろいろ!?
「普通の人々」は色んな作品に影響を与えたりしているみたいだが、観ながら自分の頭をよぎった作品を数点、あげてみたい。
「春にして君を離れ」
自分が個人的に、「普通の人々」に出てきた、カルヴィンとベスの夫婦関係にとても似ている…!と思った作品が、アガサ・クリスティ原作の「春にして君を離れ」である。
「春にして君を離れ」の主人公(一家の母親)も「外面を気にしながら自覚なく他人に支配的」な人なのだが、夫が実はそんな彼女をずっと庇いつづけている…というストーリーだ。
しかし、この映画では、カルヴィンが、「妻と向き合う」ことを選択したために、物語の結末は大きく違っている。
クリスティ作品の方が古いが、「春にして」が好きな人は「普通の人々」もヒットしそう…と勝手だが思う。
「スティール・ボール・ラン」(ジョジョ7部)

STEEL BALL RUN ―ジョジョの奇妙な冒険Part7 コミック 全24巻 完結セット (ジャンプコミックス)
- 作者: 荒木飛呂彦
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2011/08/11
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 7回
- この商品を含むブログ (10件) を見る
漫画作品なのですが…。主人公・ジョニィ・ジョースターは、優秀な兄を亡くした弟だが、父親は兄だけを愛していた…という設定だ。
「普通の人々」のワンシーンが、ジョニィが亡くなった兄の部屋に入って父親に咎められるシーンに、とても似ていると思った。
「スタンド・バイ・ミー」にも同じような設定があって、荒木先生は色んな映画から引っぱってきている気がするが、どっちからかのオマージュ!?みたいなもんなのかな。観ながら唐突に頭に浮かんできました。
「ヘレディタリー」
いやあ~「ヘレディタリー」パイセンはハンパなかったっす…!
影響を受けた作品というのには納得ですわ~。
「ヘレディタリー」の一家の食事シーンのギスギス感もハンパなかったが、この映画のコンラッドと母の2人きりのシーンの、なんと恐ろしいことか。
「ヘレディタリー」は完全なバッドエンドだったが、「普通の人々」の家族は別離することで危機を回避したように思う。
なんといっても、家族が第3者(精神科)の助けを得られたのがデカい。
コンラッドが勇気を出してかけた1本の電話…。つながるかどうか、どう転ぶか…人生でこういう場面は度々ありそうなものだと思う。
ティモシー・ハットンの演技が超すごい
この映画で、コンラッドを演じたティモシー・ハットンは、1980年のアカデミー賞・助演男優賞を受賞している。

実質主役はコンラッドだし「主演でいいだろ」と思ったが、そうすると、「レイジング・ブル」のデ・ニーロとオスカー戦、被るのね…。
もう何日も寝ていないとわかる、目の下にクマのある”鬱”な表情…精神病棟で一緒だった女の子に再会しみせる心から喜んだ表情…からの、自分との気持ちの差を知り表には出さないがそれでも一気に落胆したと分かる表情…
「すげえ!」「こんな感情の細やかな変化が伝わってくるなんて、ティモシーすげえ!」と思いながら観た。
お母さんベス役の人の演技もかなりよかった。知らない女優さんだったが、エミー賞7回受賞ってすごくないですか。有名なTV女優さんなんですね。
監督がロバート・レッドフォードなのは知っていたが、過去にみた監督作はあまり心にヒットしなかったのだけれど、「普通の人々」はもう超別格だと感じた。
「刺さる人」と「刺さらない人」が分かれる映画かもしれないが、自分はすごく好きな作品だった。
ラスト、コンラッドにエールを送りたくなる。
本屋に山積みの自己啓発本読むより、コッチや!
こっちの方がめっちゃ濃いセラピー受けたみたいに感じられるすごい映画だった…!
![普通の人々 [DVD] 普通の人々 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51po%2B4-R2IL._SL160_.jpg)

