昨年新装版が出版されましたが、自分が学生の頃に読んだのは耳がハートの形をしたデザインが印象的なこの文庫本。
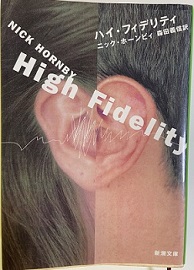
ニック・ホーンビィの本を読むのは初めてで、表紙がなんか洒落てるなーと興味を惹かれたのがきっかけでした。
大人の恋愛小説といいつつストーリーは恋人に捨てられた35歳のレコードショップ店長がひたすらウダウダしているだけ。
冒頭では「人生で辛かった失恋トップ5」をあげながら主人公ロブがこれまでの人生を振り返っていきますが、「ガールフレンドいっぱいいるし友達もいるしリア充やないかーい!」とツッコミながら読んでしまいます。
自分は音楽に全く詳しくないので主人公の言ってることはちんぷんかんぷん。
音楽好きの人たちの知識の広さや、徹底的に物を集めるコレクターの人たちの情熱に驚かされるばかりでしたが、こういうオタクのメンタリティって全世界共通なんだなーと感じ入るところも沢山ありました。
音楽でも映画でもなんでもトップ5のリストにして語ろうとする主人公と同僚のバリー。
他人のチョイスに対してはセンスがないとか知識がないとか散々こき下ろすなどオタクの嫌なところが出ています(笑)。
そういう自分も他人のあげているベストリストに自分の好きなものが入っていると同じ感性の人がいる!!と嬉しい気持ちになったり、逆に自分が好まない作品が持ち上げられていると「このベストは信用できないな」などと上から目線で思ったりすることがあります。
リスト作成には「こんな分かってる趣味のいい俺を見てくれよな!!」みたいな自己顕示欲もきっとあって、「皆とちょっと違う自分」に酔いしれる…溢れ出るオタクの選民意識。
「何が好きかでどんな人間か分かる」…
一見極端に思える主人公たちですが、しんどい時にこの作品に心を支えられたとかそういうこともあって、好きなものは自分の人生の一部なんだ、自分の人格を形成してきたものであり価値観そのものだから無下にできるもんじゃないんだ…という気持ちも分かるなあと思いました。
トップ5のリストは自分の深い部分をさらけ出す彼らなりのコミュニケーションであって、なぜ自分はこの曲を選ぶのか、この曲の何が良くてどんな思い出があるのか…リスト作成は大袈裟かもしれないけど〝自分の人生との向き合い〟みたいなものも含まれているのではないかと思いました。
主人公・ロブはDJをやっていた頃に出会った弁護士・ローラと恋に落ちますが、そのきっかけは「自分の好きな曲をいいと言ってくれた」という些細なものでした。
「自分の趣味を全て受け止めてくれる異性」を夢見るのもオタクあるある。
レコードショップの同僚・ディックは彼女が出来ると音楽の良し悪しについてガールフレンドを必死に〝教育〟しようとしていました。(悪くいえば趣味の押し付け、洗脳&調教)
好きな人に自分の好きなものを好きになってもらえるとなぜ嬉しいものなのか。
1人きりではなく誰かと一緒にシェアできるとまた格別の喜びがあるということ。
単純に相手にも喜んでもらえて嬉しいという気持ち。
自分色に染め上げたような征服感、似合う人に似合う服を着せたような達成感、素晴らしいものを自分はこの世に広められたのだというまさに「布教」の思い…そんな気持ちもちょっぴりあったりして。
ロブは気に入った女性にはおすすめ音楽を詰め込んだカセットテープをつくって送るのが常套手段ですが、「1曲目は分かりやすく惹きつけられるのを入れて、1番聞かせたいやつはあえてB面に入れて…」などと凝りに凝ってテープを完成させます。
もらった方は重いわ!!ってなりそうですが、これもトップ5リストと同じで自分の心の内を代わりに語ってもらうような、ひとつのコミュニケーションなのかもしれません。
一方、趣味が一致するからといって決して関係が上手く行くわけではない、キビしい現実も描かれています。
ローラと別れたロブは趣味嗜好が抜群に合って、ずっと付き合いたいと思っていた夢の職業〝ミュージシャン〟の女性とベッドを共にしますが、頭に浮かんでくるのはローラのことばかり。
お互い「ディーバ」が大好きだということは最初の数ヶ月で色褪せてしまった
これまでの恋愛を振り返っても、好きなものが一致してるからといって決して上手くいくわけではなかった…
友人であれ恋人であれ趣味を共有できると、会話や生活での接点が増えて良い関係が持続する1つの要素になるんじゃないかなあ、ひとつ価値観が共有できるってそれだけで尊い繋がりなんじゃないだろうか、と個人的には思います。
けど必ずしもそれだけじゃないというのもまたそうだよなあと思います。
働いたり社会に出たりすると実際助けてくれたり助け合ったりするのは趣味もなんにも関係ない人たちだったりする。
皆自分の価値観を周りと擦り合わせながらそれなりに生きてたりするもんなんだと悟る。
「好きなものだけの世界」に籠りがちだった主人公が丸くなっていく姿に自分もこんな感じでちょっとずつ年とってきた気がするなあ、と大人になって読むと余計に沁みるものがあります。
主人公ロブは浮気性だしロマンチックをいつまでも追いかけているメンドくさい男なのは間違いありません。
ロブの趣味を理解はできなくても全部受け止めて叱咤激励までしてくれる彼女さん、どんだけーなんて思ってしまうのですが、この2人、お互いがお互いにとって〝ときめく相手〟というより〝落ち着く相手〟だったのでしょう。
主人公の内心には「成功した強い男にならなくちゃいけなかったのに」というプレッシャーから来る自信のなさだったり、「もっと特別なことが待っているはずの人生」への諦めのつかなさだったりが恐らくあって、現実を受け入れていくほろ苦さもあります。
でも自分がそれなりに周りの人から信頼を勝ち得ていたこと、近くにいた人たちの大切さに気付く結末はなんだかんだでハッピーエンドだと思いました。
あれだけ拘りの強い主人公が、
「彼女の知っている曲、彼女が何度も聞いてくれる曲がたくさんつまったテープを作りたいと思う」
…と語るラストには何だかあったかい気持ちになるのでした。
映画版も原作を読んだあとに鑑賞。
元々ストーリーにはあまり起伏がないので映画としてみると終始ゆるっとした感じ。
原作にある皮肉や自虐の言い回しがイギリス男っぽいのかなと思っていたので、舞台がロンドンからシカゴに変更になっているのは残念に思われました。
けれど主演のジョン・キューザックとオタク同僚2人(特にジャック・ブラック)はハマり役。
ヒロインの女優さんはケイト・ベッキンセイルを予定していたけど妊娠で降板した…と昔雑誌で読んだ記憶があるのですが、サッパリした地味な女性のイメージだったのでイーベン・ヤイレの方が原作のローラに近くて良かったように思いました。
原作小説でも印象的な大学時代の元カノ役にはキャサリン・ゼタ・ジョーンズ。
若い時には「特別な女性」にみえてたけど改めて会ったら無駄に意識高い系&人を見下したタカビーなイタい女だったと判明する…というのが面白かったです。
原作では「ブロンドのショート」とあってもっとパンクなイメージ。自分はグウィネス・パルトロウを思い浮かべながら読みました。
原作の「もしレザボアドッグスをまだ観ていないと言ったら…」の下りが、映画では「もし死霊のはらわた2をまだ観ていないと言ったら…」に変わっていて、ジョン・キューザックの趣味でこうなったのかどうか不明ですが、ここはナイス改変だと思いました。
今読むと何もかもアナログな世界がどこか懐かしい。だけどオタクのめんどくさい自意識あるあるには今でも頷いてしまう。
こんだけ好きなものに正直でいられるのって凄いことだよなー、主人公の不器用さ、純粋さにどこか愛おしみも感じてしまうのでした。
新装版の表紙もオサレ…!!
![ハイ・フィデリティ 特別版 [DVD] ハイ・フィデリティ 特別版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wvZgYjsOL._SL500_.jpg)
